 悩める人
悩める人使用道具はなにがいるのかさっぱりわからないなぁ?
このような悩みにお答えします。
この記事の内容
二級建築士の製図で必要なオススメ道具を紹介
二級建築士の製図で必要なオススメ道具を紹介


学科に合格し次は製図、これに受からないと二級建築士資格は取れません。
チャンスは2度。2回製図受験に失敗したらまた1から学科を受けないといけないという悲しい現実が待ってます。
なんとしても一発で合格したいですよね。
それには必要な道具が揃ってないとかないません。
スタートでもたつかない為にも、
この記事を参考に最適な道具を揃えることをオススメします。
本記事では、2020年に二級建築士の製図を1発合格した筆者が
余計なものまでいろいろ買ってしまった経験をもとに、
実際に試験で使用した必要な道具をまとめました。
一部の商品は学科合格発表後に品薄になる可能性もあるので早めに揃えることをお勧めします。
製図に必要な道具は意外と種類があり購入時に迷われると思います。
私も訳が分からずいろいろ買いすぎて全く使わなかったものも存在します。
その事をふまえてオススメ道具を紹介していきます。
1.製図板
ステッドラー日本 マルスライナー平行定規 (960-A2)【smtb-s】
これがないと始まりません。試験で使えるのはこの平行定規仕様のみなので購入には注意が必要です。
2.製図用シャーペン
私はいろいろな細さのシャーペンを揃えたのですが、結局試験では0.7と0.5しか使いませんでした。
製図は時間との勝負なのでペンを持ち変える時間すらもったいなくなります。
出来れば二種類くらいで書きたいところです。
どうしても細い字で文字入れをしたい人は0.3も買っておくとよいでしょう。
ですが、0.3はその細さゆえ折れやすいです。
3.定規類
シンワ測定 三角スケール建築士用 B-30 30cm 74962
矩計図のあった年なので三角スケールは30㎝が役にたちました。
↑この形のテンプレートを常用しました。
このテンプレートはすごくオススメです。
テンプレート系は規定が細かくて、いつ禁止になるかわからないので注意が必要です。
↑このテンプレート定規も定番で良いので、どちらか一つと言われたら私なら前者。
両方揃えると完璧です。
大きい三角定規は垂直線を引く時に必要です。
短い定規を上にずらしながら線を引くことも可能ですが、
本番では焦りも出るので、ズレる可能性がゼロではないですし、
修正時間のロスを無くす為にも揃えておくべきでしょう。
木造では勾配定規も必須です。
屋根を書く時に使います。
ウチダ フローティングディスク 直径10mm 24個入り アルミ(粘着付き)
フローティングディスクは定規類の裏に貼って
滑りを良くし定規が紙に張り付くのを防ぎます。
ドラフティングテープで製図板に製図を貼り付けます。
ズレなければなんでもいいとは思うのですが、私はこれを買いました。
剥がす時も奇麗にはがせます。
字消版も使います。間違った時にこれを当てて消しゴムで消せば目的の線だけ消せます。
持っていたほうがいいです。
エスキス用紙は練習に必要なので買っておきましょう。
エスキスってなに?と思ったでしょうが簡単に言うと間取りなどのプランニング計画のことです。
サイズはA3で十分間に合いました。
その他の道具
筆記具が立てられるのでペンが取りやすくオススメです。
消しゴムのカスを払うブラシです。
これはあっても無くてもいいアイテムかな?
シャーペン芯をBで使う人は汚れやすいので必須かもしれません。
私はHB派なので持ってはいたんですが試験時は手で振り払ってました。
HBだとそんなに汚れにくいので、少しくらいの消しカスは手でいけます。


・ノック式の色ペン数色
・消せる赤ペン
ノック式はキャップ式より素早く使えるうえにキャップを落とす心配もないのでオススメです。
消せる赤ペンはエスキスの段階で消したい時が必ずあるので揃えておきたいですね。
ぺんてる Pentel 蛍光ハンディラインSオレンジ SXNS15-F


・HBのシャーペン芯
HBとBで悩む時が来ると思うのですが、Bだと手の甲で擦れた時用紙が汚れがちになるのでHBが無難です。
・消しゴム
ノック式の消しゴムが意外と活躍しました。すべて字消版を使って消すのではなく、
ノック式消しゴムで済む場合はノック式消しゴムで消してました。
時短の一環ですね。
・小さめの三角ジョーギ
矩計図の名称入れの時に斜め線を入れる際使いました。
・計算機
平米数量計算等に使います。
計算間違えは一発アウトですので、
数字の見やすい大きめのものを用意してください。
時間を見る時計も必要です。
スマホは不可なので注意です。
その他、その年にあった練習用の製図用紙が必要になります。
まとめ


製図道具は種類も豊富で迷いがちになります。
種類も豊富でまとめると結構な金額になるので、
不要なのものをできるだけ避けて時短出来るアイテムで試験に臨みたいですね!
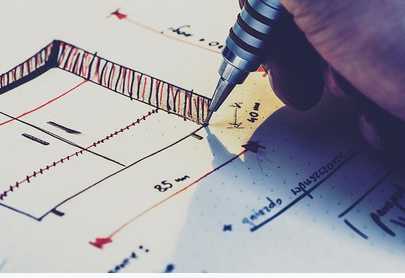












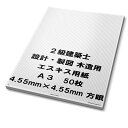





コメント
コメント一覧 (2件)
とても役に立つ情報をありがとうございます!!!!
コメントありがとうございます!
少しでも役に立ててもらえたら嬉しいです!